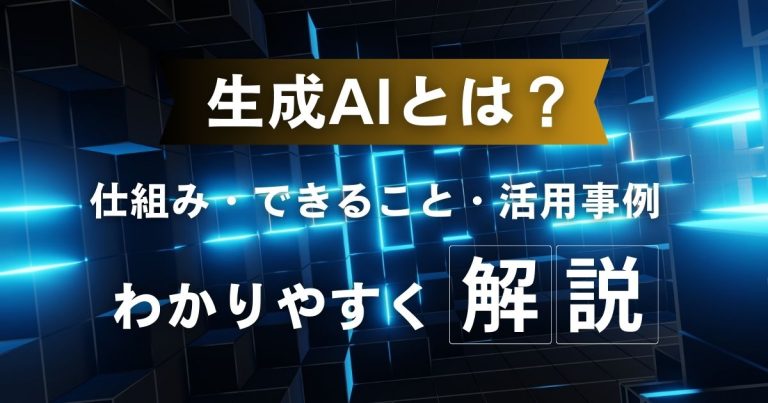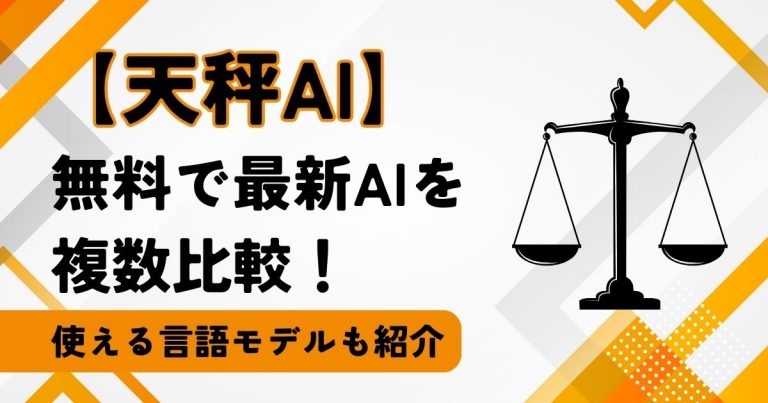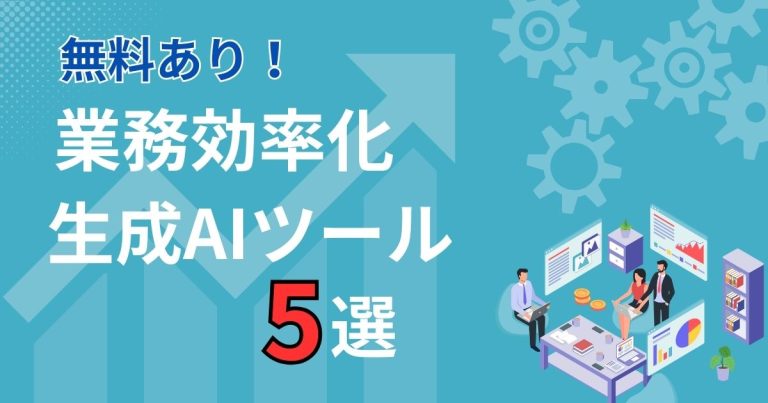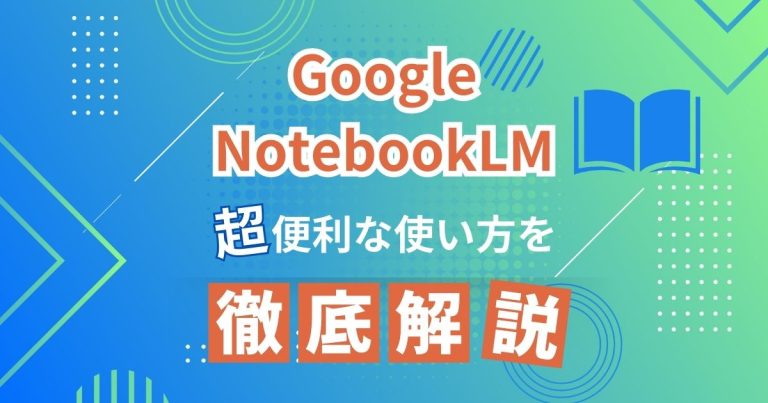【生成AI×教育業界】ChatGPT・生成AIどう使う?業務効率化への活用法
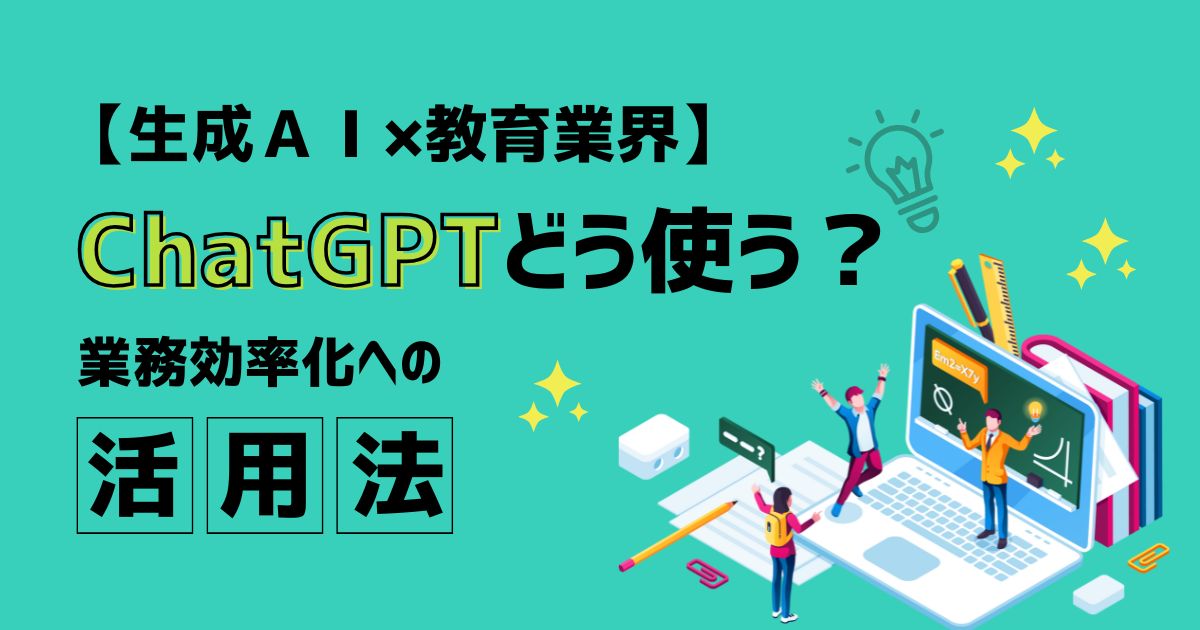
教育業界が抱える問題
教育業界が抱える問題はさまざまありますが、以下の問題は現在特に顕著に現れています。
- 教員不足とそれに伴う長時間労働
- 生徒ごとのレベルに合わせた教育指導ができない
- 授業以外の雑務が多い
その中でも特に、教員不足は業界としても大きな課題です。
文部科学省が作成した「教師不足」に関する実態調査に関する資料では、令和3年始業日時点では小中学校だけでも2,086人の教員が不足しているとなっています。
また、教員不足によって教師1人あたりにかかる仕事量が増えるため、長時間労働に悩む学校も少なくありません。こうした現状が悪循環となり、教員を目指す方も減っているのが現状です。
こういった問題を解決するためには、授業の準備やその他雑務など効率化できる部分で生成AIをうまく活用していくことが大切です。
教育業界でも進む生成AIの導入
生成AI開発の代表格であるOpenAIは、GPT-4oを搭載した大学生や教職員向け「ChatGPT Edu」を現地時間の5月30日に発表しました。これは、学生や教員を対象に、キャンパス運営における活用を支援するAIプラットフォームです。
生成AIは「教育」の分野で特に注目されており、国内の複数の教育機関では、すでに授業での試験的な導入や校務のサポートなどにChatGPTをはじめとした生成AIを活用しています。
ChatGPTを利用することで、従来の教育では実現できなかった新しい学びが可能となり、多くのメリットと効果が期待できます。
教育の現場だけでなく、世界中の企業が生成AIを活用した教育サービスの開発を進めており、より効率的に高度な学習を受けられる日もそう遠くありません。
G2のデータによると、アジア太平洋地域が教育におけるAIチャットボットの利用で先行しており、この地域の教育ユーザーの73%以上が積極的に生成AIツールを利用しているという結果が出ています。※1
参考記事
教育現場で生成AIを活用するメリット
生成AIの活用によって、学習の最適化が可能になり、生徒と教員の双方にとって大きなメリットが得られます。
具体的なメリットは大きく分けて以下の3つです。
- 教員の業務負担を軽減
- レベルに合わせた個別指導が可能
- より高度な語学学習が可能
- 外国籍の生徒への対応
それぞれ詳しく解説していきますね。
教員の業務負担を削減
学校の先生には、授業以外にも多岐にわたる業務が存在します。
例えば、授業用資料やテストの作成、通知表や調査書の作成、生活指導や進路指導、行事運営、保護者対応などが挙げられます。これら通常の業務に加え、行事運営や保護者対応など、イレギュラーな業務も多く非常に多忙です。
生成AIを活用することで、これらの業務の一部を効率化できます。例えば、各種プリントや定型文書の作成、行事の企画・進行表のドラフト作成などの自動化です。
個人面談や家庭訪問の日程調整をChatGPTに任せているケースもあり、各家庭からの希望日や住所を入力することで効率的なスケジュールをChatGPTが作成するなどの使い方もできます。
教員の働き方改革が進む中、ChatGPTの効果的な活用は大きなメリットをもたらしてくれるでしょう。
レベルに合わせた個別指導が可能
これまで、学校での「学習者一人ひとりの理解を深めるための個別教育」は難しいとされてきました。
しかし生成AIであれば、学習者の理解度に応じた個別指導が可能となり、学習者のレベルに合わせた問題を出題することができます。
さらに、学習者の質問に24時間対応可能であり、学習者のペースに合わせた学習支援を継続的に行うことが可能です。
個別教育は、学習者一人ひとりの理解を深めるための最適な方法でありながら、費用や指導者の確保の面で問題が多く実現には至っていませんでした。しかし、生成AIの登場によって今までは難しかった「学校における個別教育」という問題は解決されつつあります。
より高度な語学学習が可能
生成AIの登場により、英語の授業と教師の役割はこれからどんどん変化していきます。
立命館大学の授業では、日本語の課題文を学生、機械翻訳、ChatGPTが英訳し、学生たちはそれらを比較して表現力や思考力を向上させるという取り組みを行っています。ChatGPTの「別の言い回しを提案する」機能により、学生は新しい表現方法を学び自分らしい英語表現を身につけることが可能です。
中学生や高校生でも、ChatGPTを使えば国際会議で意見を伝える原稿を簡単に作成できる時代が来ました。ただし、ChatGPTが生成した表現を基に自分なりの英語力を身につけることが重要です。
近い将来、ChatGPTを活用して学生が自分らしい英語表現を見つける手助けをすることが、教師の役割となるかもしれません。
ChatGPTの活用が、学生の英語力向上に大きく役立つはずです。
外国籍の生徒への対応
教師や周りの生徒が外国籍の生徒の母国語を理解できていないがために、コミュニケーションに課題を抱えているケースが多々あります。
本来、すべての生徒にとって教育の機会が平等であるべきですが、外国籍の生徒に対してはその平等性を確保できていないのが現状です。
しかし、生成AIを活用することで、授業内容や教材をリアルタイムで翻訳したり、外国語での指導をサポートしたりすることが可能になり、言語の壁を超えた教育を実現できます。
生成AIを活用して生徒の文化的背景を考慮した個別の学習プランを作成し、適切なサポートを受けられる体制を整えることで、外国籍の生徒もスムーズに学習に取り組めるので、彼らの教育機会の平等性が確保できるようになるでしょう。
教育業界での生成AI活用方法9選(※ここから未修整↓
教育業界での生成AIを活用する方法をご紹介します。
- レベル別個別指導
- 英作文の添削
- 言語学習サポート
- 文章問題の作成
- テスト問題のたたき台
- 文章の校正
- リサーチの効率化
- 各授業のサポート
- アイデアの壁打ち
教育業界における生成AIの導入事例
ここでは、教育現場における実際のChatGPTの導入事例をご紹介します。
ChatGPTの導入に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
- 長崎北高校
- 愛媛大学教育学部所属中学校
- 武蔵野大学
- 東洋大学
事例①長崎北高校
長崎県立長崎北高校で、2年生約40人がAI活用ガイドラインの作成に取り組みました。※3
同校では既に英語学習にChatGPTを活用しています。
今回、生徒たちはペアでChatGPTの導入におけるメリットとデメリットを考え発表しました。あるペアは正解のある問題でのChatGPTの有効性を紹介しつつ、自分で考える力の重要性も合わせて強調。別のペアは、架空の寸劇を通じてAIの限界を示し、情報の参考としての活用を提案しました。
さらに、学校現場における生成AIの使用について文部科学省が発表したガイドラインについて、AI活用の賛否を英語で討論し、音声入力の限界にも言及しました。同校の英語担当の上村教諭は「ルールの必要性と中間の視点の重要性」を訴えています。
事例②愛媛大学教育学部附属中学校
愛媛大学教育学部附属中学校・理科担当の真木先生は、生徒の振り返りへの対応時間を短縮するためにChatGPTを導入しました。※4
生徒たちはタブレットを使い、授業の成果や疑問を専用フォームに記入し、振り返りを行います。ChatGPTによるコメントは、例えば実験の失敗に関するコメントには「素晴らしいチャレンジ精神」などと称賛があるように、事前に簡潔で肯定的な内容にするよう指示されています。
AIを使うことで迅速かつ多くのフィードバックを提供できるようになった一方で、AIの回答には誤りが含まれることもあり、その都度先生はコメントを確認し必要に応じて修正する必要も。
AIはあくまで補助的な道具であり、教員が生徒の疑問や学びに合わせて判断しながら使うことが重要だと真木先生は強調しています。
事例③武蔵野大学
武蔵野大学は、創立100周年記念事業とDX推進の一環として、生成AIを搭載したICTヘルプデスクチャットボットを導入しました。※5
生成AIの導入により、従来のチャットボットに比べ自然で高度な対話が可能となり、利用者は迅速かつ正確な情報を得られるようになります。将来的には、利用者の対話履歴や個人データを活用し、パーソナライズされた情報提供を目指します。
新しい生成AIチャットボットは、利用者のフィードバックを反映して継続的に学習・改善し、効果的なサポートの提供が可能です。
また、ICTヘルプデスクチャットボットには、データのセキュリティとプライバシー保護のため、Microsoft社の「Azure OpenAI Service」を利用しています。
事例④東洋大学
東洋大学情報連携学部(INIAD)は、全学生にGPT-4を使用させるためのAI教育システム「AI-MOP」を開発・導入しました。※6
このシステムにより、学生はGPT-4を利用して自分の考えを深め、高度な思考力を養うことができます。
学生はSlackボットを介してChatGPTを利用し、質問解決や研究に役立てることが可能です。
このシステムは、APIを使ったプログラミング教育をサポートし、バグによるコスト爆発を防ぐ仕組みを備えています。送信データはOpenAIのサーバーに保存されず、安全面にも配慮。INIADは今後、ほかの様々な生成AIにも対応し、最新のAI技術を迅速に取り入れた学習環境を提供することを目指しています。
教育業界で生成AIを導入する際の注意点
教育現場でChatGPTを導入する際に、注意しなければいけない点がいくつかあります。
ユーザーのフィードバックや開発者側の努力により大きく改善されてきていますが、それでも生成AIを使うリスクは0ではありません。
ChatGPTを活用する際には、主に以下の3つのことに注意が必要です。
- 個人情報流出のリスク
- ハルシネーションを起こす可能性がある
- エラーを起こすことがある
1つずつ解説していきます。
個人情報の流出リスク
ChatGPTを利用する際には、個人情報の取り扱いに十分注意が必要です。
ChatGPTは入力された内容をモデルの学習に流用することがあり、適切なセキュリティ対策が取られていないと入力した情報が第三者に漏洩する可能性があります。
安全性を考慮してデータを学習に使わないものもありますが、氏名や住所、電話番号などの個人を特定できる情報は絶対に入力しないことが重要です。また、機密情報や企業秘密を含む内容も含めないように注意してください。
ハルシネーションを起こす可能性がある
ChatGPTは高度な自然言語処理能力を持っていますが、時には誤った情報や架空の事実を生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。
これは、モデルがトレーニングデータに基づいて最もらしい回答を生成する一方で、現実と異なる情報を含む可能性があるためです。
ユーザーは生成された情報を鵜呑みにせず、特に重要な決定を行う前には必ず事実確認を行ってください。ユーザー自身が信頼性の高い情報源と照らし合わせ正確性を確保することで、誤情報によるリスクを最小限に抑えることが可能です。
ChatGPTの限界を理解し、適切なフィルタリングと判断を行うことが重要です。
エラーを起こすことがある
ChatGPTは、まれにエラーを起こし意図しない回答や動作をすることがあります。
特に、授業で利用する際に不具合が発生すると、授業が中断されるリスクも。こういった問題に対処するため、教員はChatGPTについて熟知しておく必要があります。
また、エラーが発生した場合に備えて代替手段やバックアッププランを用意しておくことも大切です。現時点でのAI技術の限界を理解し、活用する際には適切な対応策を検討したうえでうまく活用しましょう。
ChatGPTを教育現場に導入しよう
ChatGPTは、すでに国内でも多くの教育機関で試験的に導入され、授業や校務のサポートに活用されています。
ChatGPTの登場により、教員の業務負担削減、個別指導、高度な語学学習、さらには従来の教育方法では実現できなかった新しい学びの実現も不可能ではなくなりました。
実際の事例として、長崎北高校や愛媛大学教育学部附属中学校などが挙げられ、効果的な活用法が示されています。
ただし、導入にあたっては個人情報流出や誤情報生成(ハルシネーション)、エラーリスクに注意し、適切な対策を取ることが大切です。
ChatGPTの活用は、学習の質を向上させる大きな可能性を秘めています。教育現場での導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
参考記事